
バイク用の初心者マークはいらない?メリットやおすすめの表示位置を紹介
四輪車には免許取得から一定期間は初心者マークをつけることが義務付けられていますが、バイクにも初心者マークをつける必要があるのでしょうか。
また、バイク専用の初心者マークがあるのか分からないという方もいるでしょう。
本記事では、バイク用初心者マークの表示義務や表示場所、得られる効果について解説します。
結論として、バイクの免許を取得しても、四輪車のように初心者マークの表示義務はありません。
しかし、初心者マークをつけることで様々なメリットを得られるため、この記事を参考に初心者マークの必要性について理解していただけたらと思います。

初心者マークをご存じの方は多いかと思いますが、正式名称は「初心運転者標識」です。免許取得から1年未満のドライバーであることを周囲の車に伝えるために、車に貼り付けて使う標識です。若葉マークとも呼ばれ、縦18.5cm、横11.6cmのものを地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見えやすい位置に、全面後面の両方につける必要があります。
初心者マークの表示は、運転免許取得後1年間は初心者マークを車に貼り付けることが道路交通法第71条5で定められています。
そのため、たとえ車の運転技術が優れていたとしても、期間中は車の定められた位置に初心者マークを貼りつけなければならないのです。
義務期間に初心者マークをつけないで走行すると、初心者標識表示義務違反として以下の罰則が科せられます。
指定された場所以外に貼りつけたり、車の前後両方に貼らなかった場合も同じ罰則に問われるため、注意しなければなりません。
初心者マークをつけた車が走行していると、周囲のドライバーはその車に配慮することも義務付けています。
初心者マークをつけている車に対して、無理な幅寄せや割り込みを禁止しており、この法律に違反した場合、普通車であれば違反点数1点、反則金6,000円の罰則が科せられます。
つまり、車は初心者マークをつけることで安全に走行できるよう守られているのです。

四輪車の初心者マークは見たことがあっても、バイクに初心者マークがついているのを見たことがない、という方もいるでしょう。
しかし、バイク用の初心者マークも存在します。
バイクショップなどに車用のものが小型化されたバイク用の初心者マークが販売されています。
「バイクの初心者マークを見たことがない」と思う方が多いのは、実際にバイクに貼り付けている人が少ないためです。
「バイクに初心者マークをつけないのは違反ではないか」と思われがちですが、実は、バイクには初心者マークの表示義務はありません。
そのため、たとえバイクに初心者マークをつけていなかったとしても、罰せられることはありません。
ちなみに、高齢者マークとして知られる「四つ葉マーク(正式名称:高齢運転者標識)」は、70歳以上の人が車を運転するときに貼りつけるのを努力義務となっていますが、こちらもバイクに乗る際には表示義務がありません。
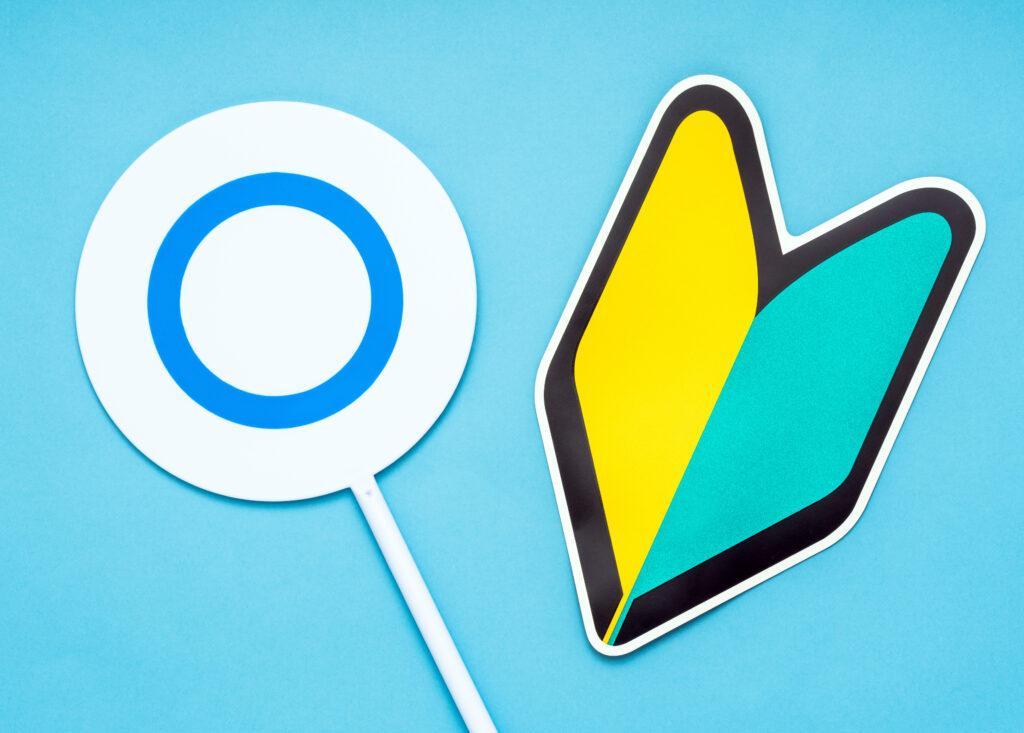
たとえバイクに初心者マークをつける義務がないとしても、免許を取得したばかりの人は初心者マークを表示して周囲に注意を促すのがおすすめです。
なぜなら、バイクは四輪車よりも事故の際の損害が大きくなりやすく、命を落とす危険性も高いからです。
ここでは、バイクに初心者マークをつけるメリットについて説明していきますので、必要性について考えてみましょう。
バイクに初心者マークをつける大きなメリットは、周囲に運転が不慣れであるということをアピールできる点です。
四輪車と同様、バイクも初心者マークを表示していれば、それに気付いた周囲のライダーやドライバーは気を遣う運転をしてもらえるケースが多くなります。
幅寄せや進路妨害、煽り運転などの危険な行為をされる可能性が低くなり、車間距離をあけてくれることもあるでしょう。
初心者マークをつけない場合より、安心してバイクを運転できるはずです。
周囲のドライバーやライダーが、初心者であることを認識することで、より配慮深い運転をしてくれることが期待できます。
例えば、幅寄せや進路妨害、煽り運転などのリスクが低減され、車間距離を保ってくれることも多くなるでしょう。このように、初心者マークは安全性を高める重要な手段と言えるのです。

バイク初心者の人で、公道での走行に不安を感じる方は多く、不慣れであるが故に立ちゴケやエンストなどのトラブルを起こしやすく、その際にうまく対処できないことがあるでしょう。
ですが、初心者マークの存在に気付いてもらえたら、周りにいるライダーや車のドライバーに助けてもらえる可能性が高くなります。
仲間とツーリングに出かけるならそれほど心配はいりませんが、ソロツーリングを行う際は初心者マークが大いに役立つはずです。
初心者マークを身につけていることで、周囲のライダーや車のドライバーに気付いてもらいやすくなります。特にソロツーリングをする際には、安全面で大きな利点となるでしょう。
初心者マークをつけることは、他のドライバーに自分のドライバーとしての経験値を知らせる手段でもあります。
バイクに初心者マークをつけていると、後ろの車が気付いて車間距離をとってくれるケースが多いです。
そうすると、余裕を持って安全に車線変更をすることができます。
バイク初心者の方は、安心して運転できるようになるでしょう。
初心者マークの表示は周りはもちろん、自分自身にバイク初心者であることを認識させるという意味でも役立ちます。
自分がまだバイク運転に慣れていないと自覚すれば、安全運転を心掛けるようになるでしょう。
バイクの基本を押さえることが初心者にとって上達への近道となるため、免許を取ったばかりだという自覚を高めるためにも、初心者マークをつけるのがおすすめです。

バイクは四輪車と違い、初心者マークの表示位置は定められていません。
しかし、バイクが操作しづらくなる場所や、保安部品を隠してしまう場所、ナンバープレートの文字が見えなくなるような場所に貼りつけないよう注意しましょう。
バイクに初心者マークを効果的に表示できる場所を紹介します。
四輪車の場合、前後両方に初心者マークをつけるのが義務付けられていますが、バイクにはそれがないため、どこに何枚つけても良いということになります。
バイクも前後に表示すれば、前方からも後続車にもアピールできますが、どちらかに貼るならバイクの後方がおすすめです。
後方の方が初心者マークの存在がドライバーに認知されやすく、配慮してもらえる可能性が高くなるでしょう。
後方であれば、泥除けなどが適しています。
初心者マークの取りつけは、バイク本体でなくても良いため、ヘルメット後部やリュックなどに貼るのもおすすめです。
バイクは四輪車に比べると小さいため、周りからマークを認識してもらうためにも、目立つ位置に表示させる必要があります。
そのため、高い位置にあるヘルメットやリュックに貼るのは車体の低い位置に貼るよりも効果が期待できます。
バイクでの荷物の積載に使うリヤボックスを取りつけている場合、そこに初心者マークを貼るのも良いでしょう。
サイズが大きく目立ちやすいリヤボックスに貼っておけば、後ろのドライバーにも気付いてもらいやすいです。
ステッカータイプの初心者マークがありますが、車体にステッカーの糊残りがつくのが心配な方にもおすすめです。

バイクは四輪車と違って範囲が少ないため、初心者マークを貼る場所によっては、事故に繋がるほか、違反になる恐れもあります。
初心者マークを貼ってはいけない場所はこちらです。
また、車体の低い位置に初心者マークを貼っていても、周りのドライバーから認知されないため、「目立つ場所」「高めの位置」に表示するのを意識して位置を選ぶようにしてください。

四輪車に貼る初心者マークはバイクに貼るには大きすぎて不向きです。バイク用品店などでは小型化されたバイク用の初心者マークが多数販売されています。
バイク用の初心者マークは、以下4つのタイプが主流です。
中でもマグネットタイプが多く販売されていますが、実はバイクへの貼り付けには向いていません。
それぞれの特徴を詳しく説明していきますので、自分に合った初心者マークを選びましょう。
車のステンレス部分につけるのを想定して作られたマグネットタイプの初心者マークは、バイクへの貼り付けにはあまり適していません。
バイクにはステンレス部分が少なく、つけても走行中に剥がれてしまう可能性が高いからです。
そのため、後述する他のタイプの初心者マークを貼るのが良いでしょう。
バイクに初心者マークを貼るのであれば、マグネットタイプよりもステッカータイプのものが適しています。
ステッカータイプは様々な大きさのものがあり、バイクのサイズや取りつける場所に合わせられるでしょう。
また、透明なフィルムで保護されているタイプのステッカーもあり、耐久性が高く、長期間使用しても色あせしにくいです。
何度も貼って剥がせるタイプもあるため、バイクが上達したら簡単に外せます。
ただし、粘着タイプのステッカーは、はがすときに糊が残る場合があります。
バッジタイプ
衣服やリュックなどに初心者マークを取りつけるならバッジタイプも良いでしょう。
バッジタイプなら取り外しも簡単で、着るものや荷物が変わってもつけやすく外しやすいです。
バッジタイプの初心者マークにも様々な種類があり、ファッションの一部として楽しむライダーもいます。
ステッカータイプの糊残りやバッジタイプの穴の跡が気になる方は、バイクのナンバーフレームに取りつけるタイプの初心者マークがおすすめです。
マークの形をしたステンレスステーをナンバープレートのボルトに共締めし、専用のステッカーを貼るだけで取りつけられます。
一度取りつけたら自分で外さない限りは簡単に外れません。

いくらバイクに初心者マークをつけたからといって、安全が保証されるわけではありません。
ここでは、バイク初心者が特に注意すべきポイントをご紹介します。
バイクの点検やメンテナンスを怠ることは、車体に何らかのトラブルが発生し、大きな事故につながる危険性があります。
バイクには12ヶ月点検や24ヶ月点検といった法定点検や車検が義務付けられているため、忘れずに実施するのはもちろんのこと、それ以外にも定期的な点検やメンテナンスを行うようにしましょう。
特に、燃料やタイヤ、ライト、バッグミラーなどは走行前に確認するのがおすすめです。
交通量が多い時間帯はバイクの事故が発生しやすいため、通勤・帰宅ラッシュの時間帯である8時~10時、16時~18時の間は特に注意して走行する必要があります。
特に金曜日は、自分はもちろんのこと、周りのライダーやドライバーも疲れが溜まりやすく、注意力も低下してしまいがちなので、気をつけて走行しましょう。
また、急いでいると運転が荒くなりやすいため、時間に余裕を持ち、早めに家を出るなどの対策をとるのも有効です。
雨の日は視界が悪くなり事故が発生しやすくなります。
また、バイクがスリップしやすくなるため、普段よりもスピードを落として走行するほか、急ブレーキをかけないよう注意してください。
また、足場が悪くなる道路の端など水溜りができやすい場所やマンホールの上、白線の上などでの走行を避け、道路の中央を走行するようにしましょう。
さらに、雨天時には後続車両との距離を広く取ることも重要です。後続車両が追突するリスクを減らすために、ブレーキランプが効果的に見える位置にいることを確認しましょう。

バイクには初心者マークの表示義務はないため、貼りつけるかどうかはライダー自身の判断に委ねられます。
ですが、バイク用の初心者マークは四輪車より小さく目立ちにくいものの、周囲にマークをアピールできたら、いざという時に役立ちます。
ですから、運転にまだ慣れていない、久しぶりで運転に自信がないライダーの方は初心者マークを貼っておくと安心です。
初心者マークをつけることで、他のドライバーに自分の経験レベルを伝えることができ、思わぬ誤解や事故を防ぐ役にも立ちます。周囲のドライバーに対しても配慮を示すことができ、道路での円滑な共有が促進されるため、初心者マークをつけることで、より安全で安心なバイクライフを送れるでしょう。
全国60店舗以上ある2りんかんでは、ライダーの求める様々な商品をお取り扱いしております。
バイクが大好きなスタッフが、あなたに合った商品を提案させていただきます。
https://2rinkan.jp/shop/index_list.html