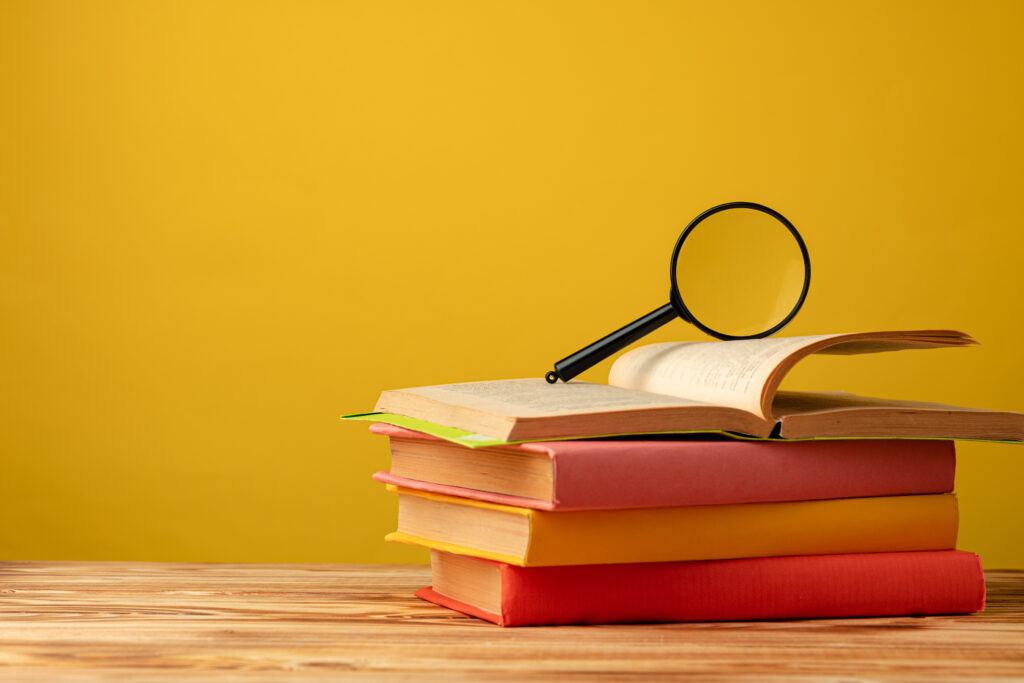
バイクの基礎知識として覚えておくべき名称とは?バイクに乗る上で覚えておくべき用語も解説
バイクの基礎知識として覚えておくべき名称について知りたいと悩んでいませんか?
この記事では「バイクの基礎知識として覚えておくべき名称」について紹介します。
他にも「バイクに乗る上で覚えておくべき用語」や「シーン別バイク走行中に気を付けるポイント」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、バイクの基礎知識について理解を深めてみてください。
バイクの基礎知識として覚えておくべき名称については、以下があります。
それぞれの名称について解説していきます。
エンジンは、400ccや1000ccなど「排気量」が設定されており、排気量が大きくなるとよりパワフルな走行が可能です。
排気量(※)とはエンジンが吸い込むことができる空気と燃料の容積のことです。
※シリンダー容量の合計。単気筒、多気筒があり、シリンダーの数でわけられます。
日本のバイクの免許区分は、以下のエンジンの排気量で分類されています。
バイクのフレームによってエンジンの設置方法は異なりますが、基本的にはタンクの下にエンジンが設定されてあることが大半です。
バイクを動かすために必要な部品として、バッテリーが挙げられます。
近年、電子制御のあるバイクも多く、バッテリーがなければバイクを始動させることはできません。
また、ライトやウインカーも点けることができません。
そのため、エンジンのかかりが悪い場合には、バッテリーが劣化している可能性が高いです。
バッテリーには、スマートフォンなどのモバイル端末のように定期的な充電は必要ありませんが、長期間バイクを動かしていない時などは自然放電でバッテリーが弱ったり、使えなくなっていたりする場合もあります。
そのような状態になってしまったら、専用のバッテリー充電器で充電・もしくは交換する必要があります。
サスペンションとは、車体とタイヤを繋ぎ、特殊なスプリングやダンパーと呼ばれる装置でバイクを支えている部品のことを指します。
具体的には、リアタイヤ&スイングアームと繋がっている「リアサスペンション」とフロントタイヤと繋がっている車体前方の「フロントフォーク」の2種類によって構成されています。
サスペンションは、走行中に路面に凹凸がある場合でも、衝撃を吸収・緩和することで、快適かつ安全にバイクを走行させることができる重要な部品です。
実際に、サスペンションによってバイクの操縦安定性や乗り心地が大きく変わるのも事実です。
自分好みのフロントフォークやサスペンションを選ぶことによって、バイクを走行中の体への負担を減らすことにもつながります。
チェーンとスプロケットは、エンジン内で生み出された動力を駆動輪(後輪)に伝えて、リアタイヤを動かすための部品です。
バイクを走らせることで高速で回転し、少しずつ摩耗していくので、長持ちさせるために定期的にメンテナンスや交換が必要になります。
また、現在は多くのバイクに採用されているのは「チェーンドライブ」です。
車両メーカーや車種により、ベルトを使用した「ベルトドライブ」、シャフトを使用しメンテナンスをラクにする「シャフトドライブ」等があります。
エアクリーナーは、エンジン内に綺麗な空気を送り込む目的がある部品です。
バイクのエンジンは、ガソリンと空気を混ぜた「混合気」をエンジン内で圧縮して爆発させ、そのエネルギーによって動きます。空気中のチリやゴミを取り除いてくれるフィルターがあることによって、エンジン内の汚れを抑えることにもつながります。
エアクリーナーには、フィルターが乾燥している乾式フィルター、オイルで湿らせてある湿式フィルターの2種類があります。
バイクの車種によっても形状が異なります。
ホイールとタイヤは、エンジンの力を路面に伝える役割があり、摩擦力によってバイクを走行させたり、コントロールしたりする重要なパーツです。
タイヤの構造には大きく分けて以下の2種類があります。
ラジアルタイヤとは、操縦性や安定性が高くスポーツ走行などに適しているタイヤです。
バイアスタイヤについては、低速走行や悪路走行などに適しています。
タイヤはバイクに最適なタイヤサイズで設計されており「ホイール」の大きさによっても乗り心地が大きく異なります。
また、安全面や燃費性能なども担っている非常に重要性が高い部品となります。
インジェクションとは、ガソリンの噴出量を電子制御する部品です。
キャブレターについては、機械制御するものがキャブレターになります。
基本的に国内モデルであれば、2000年代以降のバイクはインジェクションが使用されており、それ以前のバイクはキャブレターが採用されています。
どちらとも機能的には同じですが、キャブレターの場合は、放置している期間が長くなってしまうと、キャブレター内部のガソリンが劣化してしまい、エンジンがかからなくなってしまうリスクがあります。
そのため、バイクに乗る機会がなくても、定期的にエンジンをかけるクセをつけておきましょう。
フレームとは、アルミ合金やスチール作られいます。バイクの骨格そのものであり、地面やエンジンからの衝撃を吸収したり、重いパーツを支える役割があります。
フレームの形はバイクの車種やメーカーなどによって大きく異なります。
マフラーとは、排気ガスを外に放出するパーツで、排気ガスの清浄化と消音などの役割があります。
また、素材によって音質や見た目が大きく変わるので、自分だけのカスタムをしたいという人におすすめです。
走行中は高温になるので、触ってしまうと火傷してしまうので、触らないように注意が必要です。
バイクに乗る上で覚えておくべき用語については、以下があります。
それぞれの用語について紹介していきます。
押しがけとは、バッテリーが上がってセルが回らないときに、バイクを押してエンジンをかける方法のことを指します。
具体的なやり方については、以下のとおりです。
押しがけするコツは、クラッチを一気に繋ぐことと、バイクを押す場合に全体重を車体に預けて押すことです。
千鳥走行とは、集団でのツーリングなどで複数のバイクで走るときに用いられる走行方法です。
走行車線の中で右と左の2列縦隊となり、互い違いになるように位置取りして走行します。
バイク同士が車間距離を保つことができ、お互いが視認しやすくなるのがメリットといえます。
一列走行の場合だと、隊列が長くなってしまうので、追突のリスクがあるのも事実です。
一方、千鳥走行だと互い違いになるため、車間距離を確保しつつ全体の隊列を短くすることができたり、信号などで分断される可能性を低くすることが可能です。
また、ミラー越しに後ろのライダーの顔が見える位置になるので、メンバー同士がお互いの状況を把握しやすくなる特徴があります。
すり抜けとは、バイクが車と車の間や路側帯をすり抜けて通ることを指します。
実際に、すり抜けは違反になるケースが多く、事故のリスクも高まります。
すり抜けという行為は追い越しもしくは追い抜きとなりますが、以下のように追い越しが違反として定められています。
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
参考元:道路交通法第30条
上記のように、追い越しをする際には、違反にならないように注意が必要となります。
ライディングポジションとは、バイクの乗車姿勢のことを指します。
ライディングポジションが良くないと、体に負担がかかってしまい、疲れやすくなったり、瞬時の判断が遅れてしまい大きな事故につながってしまうリスクがあります。
実際に、バイクの車種やライダーの体格などによってライディングポジションは大きく変わります。
基本的なライディングポジションは、以下の3ヶ所の位置関係で構成されています。
また、ライディングポジションは運転のしやすさや快適性のほか、コーナリング特性にも大きく関わってくるので重要なものといえます。
立ちごけとは、停車中にバイクにまたがったままバランスを崩して転倒してしまうことです。
バイクを押している時や停止直前などでほぼ速度ゼロという状態で転倒した場合についても、立ちゴケと呼ばれています。
実際に、立ちゴケをしてしまうと、部品が破損してしまうことが多く、車両の下敷きになってしまうと骨折の恐れもあります。
シーン別バイク走行中に気を付けるポイントについては、以下があります。
それぞれのポイントについて解説していきます。
雨の日は、視界が悪くスリップしやすくなっているので、事故がもっとも多い場面といえます。
特に、マンホールの上や白線の上を走行するときは注意が必要なのはもちろん、急にブレーキをかけると転倒してしまう危険があります。
マンホールや白線をできるだけ避けて走行して、避けられない場合には十分スピードを落とすようにしましょう。
また、道路に水がたまり、路面とタイヤの間に水が入るため、タイヤが滑ってブレーキが利かなくなる「ハイドロプレーニング現象」が発生してしまう危険性もあります。
このように、事故を防ぐためにも、雨の日はなるべくバイクで走行するのは避けるようにしましょう。
交差点は歩行者が行き交う上、曲がり角は見通しが悪いので、事故が起きやすい場所といえます。
実際に、信号が変わる直前にスピードを出して滑り込む車や駆け足で渡ろうとする歩行車がいるのも事実です。
交差点での衝突事故を起こさないためにも、交差点に近づいたら必ず一時停止するよう心がけましょう。
また、交差点は巻き込み事故や右直事故が多い場所なので、車間距離を十分に取り、対向する車の動きや走行速度の出し過ぎに注意をして走行するようにしましょう。
高速道路を走行するときは、常に走行状態になるので、少しの判断が遅れてしまうと、大きな事故につながってしまいます。
車体に何かしらの不具合が起きてしまうと、事故に発展してしまう可能性があるので注意が必要です。
具体的には、以下の項目のチェックをするようにしましょう。
また、高速道路では車間距離を長めに取ることも重要といえます。
万が一、前の車が急停車したりスリップを起こしたとしても、衝突を防ぐことができ、被害を最小限に抑えることにもつながります。
今回は、バイクの基礎知識として覚えておくべき名称やバイクに乗る上で覚えておくべき用語を紹介しました。
バイクの基礎知識として覚えておくべき名称については、以下があります。
また、シーン別バイク走行中に気を付けるポイントを把握しておくことによって、事故のリスクを最小限に抑えることにもつながります。
今回の記事を参考に、バイクの理解を深めて楽しいライディングをしましょう。